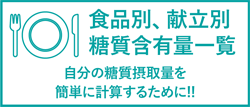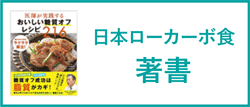日本には覚せい剤が蔓延している?2
日本には覚せい剤が蔓延している?「世界の薬物汚染マップ」でわかった、日本の実態!2
じん薬局 加藤 仁 記
前回からの続き
前回 https://www.low-carbo-diet.com/whats_new/blog-katoujin3
■日本で流行する覚せい剤
他の麻薬と比べれば、20世紀初頭に流通が始まった覚せい剤の歴史は長いとはいえないが、わが国における乱用の歴史は古く、根深いものがある。日本における覚せい剤流行のきっかけとなったのが、1941年に大日本製薬(現在の大日本住友製薬)が発売したヒロポンである(現在でも医療用医薬品として存在する)。
ギリシア語の「ピロポノス」(“労働を愛する”の意)を商品名の由来とするヒロポンは、疲労の回復や眠気の解消等の効能をうたい、町の薬局・薬店でさかんに売り出された。さらに、発売と同年に開戦した第二次世界大戦の影響により、戦闘への利用を計画した旧日本軍がヒロポンを調達し、本土決戦のために備蓄していた。
しかし1945年の敗戦を機に、備蓄されていたヒロポンは闇市などを通して大量に市場に放出され、無数の中毒者を生み出す結果となった。ヒロポンの危険性を認知した政府はまもなく流通を遮断したが、以後はヤクザ・暴力団を中心とする非合法組織が架け橋となることで、韓国・北朝鮮・台湾などの諸外国から購入者の手元へ、ヒロポンと同様のアンフェタミンを主成分とする覚せい剤の密輸が続いている。
近年では法規制をかいくぐった危険ドラッグや、MDMAなどの合成麻薬の乱用が取り沙汰されることも多くなったが、薬物犯罪で摘発される著名人に関していえば、旧来通りの覚せい剤の使用によって検挙されるケースが目立つ(高知東生、清原和博、酒井法子、ASKA、槇原敬之、清水健太郎、田代まさし、などなど)。こうした傾向は、日本に麻薬=覚せい剤という、好ましくない歴史と文化が根付いてしまったことを証明するものだと思う。
■荒れ野に連なるケシの花:EU諸国にまん延するアヘン
ヨーロッパ全域からユーラシア大陸にかけて非常に広範囲をカバーしている麻薬は、ケシに由来するアヘンとその化合物である。子どもの背丈ほどに成長するケシは、晩春から初夏にかけ大輪の花をつけ、やがて花が枯れると子供の握り拳ほどの大きさの果実、いわゆる“芥子坊主”を残す。このケシの果実を刃物で傷つけることで採取できるのが暗褐色の粘液である生アヘンだ。
ヨーロッパに流通するアヘンの一大供給地は、イランとパキスタンの国境線を結ぶ「黄金の三日月地帯」である。特に両国の中央に位置するアフガニスタンでは、2001年のアメリカによる軍事行動を境にアヘンの生産量は年々増加し、いまや世界で使用されるアヘンの80%がアフガニスタンから出荷されていると言われている。
アフガニスタンの国土に占める耕地の割合はわずか12%に過ぎないが、国民の70%が農業を営んでいるという事実があり、内戦下で困窮する農民たちの生活を支えるのは、穀物やフルーツの栽培ではなく容易に換金可能かつ多額の収入をもたらすケシの栽培に他ならない。
米軍の攻撃で政権の座を追われたイスラム武装組織タリバンは、2000年以降ケシの栽培を禁止しており、翌年には3,276トンあった生産量が185トンへ激減するなど取締りの成果が上がっていた。ところがアメリカ主導による新体制の下では息を吹き返すケシ栽培・アヘン製造の流れに歯止めがかからず、有効な手立てを打ち出すことができずにいる。アフガニスタンで生産されたアヘンは、陸路をゆき大陸中を移動する。水際での阻止も重要だが、生産地に手を伸ばして現地の貧しさを解消しない限り、ヨーロッパの先進諸国へアヘンの流入が止むことはないだろう。
■タバコより有害性が低い? 緩みゆくマリファナの規制事情
オーストラリアやカナダ、アフリカ諸国で目立つのが、麻薬の中では最も原始的な部類に含まれるマリファナである。特徴的な形をした大麻草の花冠や葉っぱを乾燥させ、まれに樹脂として精製することもあるが一般的には紙で巻いたり、単純な構造の水パイプ“ボング”を利用して喫煙される。日本をはじめ、多くの先進国で使用は禁じられているが、オランダやポルトガルなど限られた国では身体的な被害や依存性の薄い“ソフトドラック”として合法化されている。地図において色づいているオーストラリアなども一部の州で合法、その他少量所持なら合法などという国もあり、ところによっては懲役に至らないごく緩やかな取締りが行われている場合もあるようだ。
マリファナが合法・半ば非合法といった玉虫色の取り扱いを受けるのは、科学的な検証を根拠としアルコールやタバコより有害性が低いと断じる報告が医学誌に掲載されるなど、日を追うごとに高まりを見せるマリファナ擁護の動きに習ってのことだ。ただし、マリファナがより危険性の高い麻薬へアクセスするための“進入路”として機能することを危惧する「ゲートウェイ・ドラッグ理論」の展開などもあり評価は一定していない。
実際にニュージーランドだけでも1万4,000人を超える中毒者を生み出すなど、その影響は軽視できるレベルとはいいがたい。さらにはマリファナ中毒の治療のために、コカインをはじめとする別種の麻薬の使用を余儀なくされるといった悪循環をも生み出す。「気安く手を出してもよいか?」と問われたなら、首を縦に振るのはためらわれてしまう。
マリファナの主要な生産地は、武装した麻薬カルテルが暗躍し治安に深刻な問題を引き起こしているメキシコだ。だがここ最近では、アメリカのカリフォルニア州を中心にビジネスとして合法的に栽培を行う計画が相次いで実施されている。マリファナの健康被害の懸念は前述の通りだが、商業栽培が軌道に乗ることで流通面に関しては犯罪性を排除した製品へ需要が移り変わる余地があるだろう。
■進展する中毒者の高齢化
さて、ここまで世界に広がる麻薬について見てきたが、最後に興味深い研究をひとつ紹介したいと思う。これまで麻薬の中毒者といえば鼻から粉末を吸い込む若者のイメージで通ってきたが、そうしたステレオタイプは次第に現実とかけ離れつつあるそうだ。
アメリカきっての大都市であるニューヨークで実施された研究の結果、米国における中毒者の半数は50歳以上のベビーブーマー世代で占められている可能性が高いことが明らかとなった。1996年には治療を受けている患者集団の56.2%は40歳以下だったが、2012年には20.5%までその割合は低下している。麻薬の愛用者たちにも高齢化の波が及んでいるのだ。
この研究結果については、若い世代が麻薬に対する興味を失いつつあると解釈することもできるだろう。もっとも、50歳以上の患者数は同期間で激増しているため、単なる年齢層のシフトに過ぎないとも言え、予断を許す状況ではないのだが。
今後も麻薬との戦いは続くが、麻薬を生み出さず、使わず、後の世代に連鎖させない未来が一刻も早く訪れることを心から願いたい(ただし、医療用麻薬はこの限りではない)。